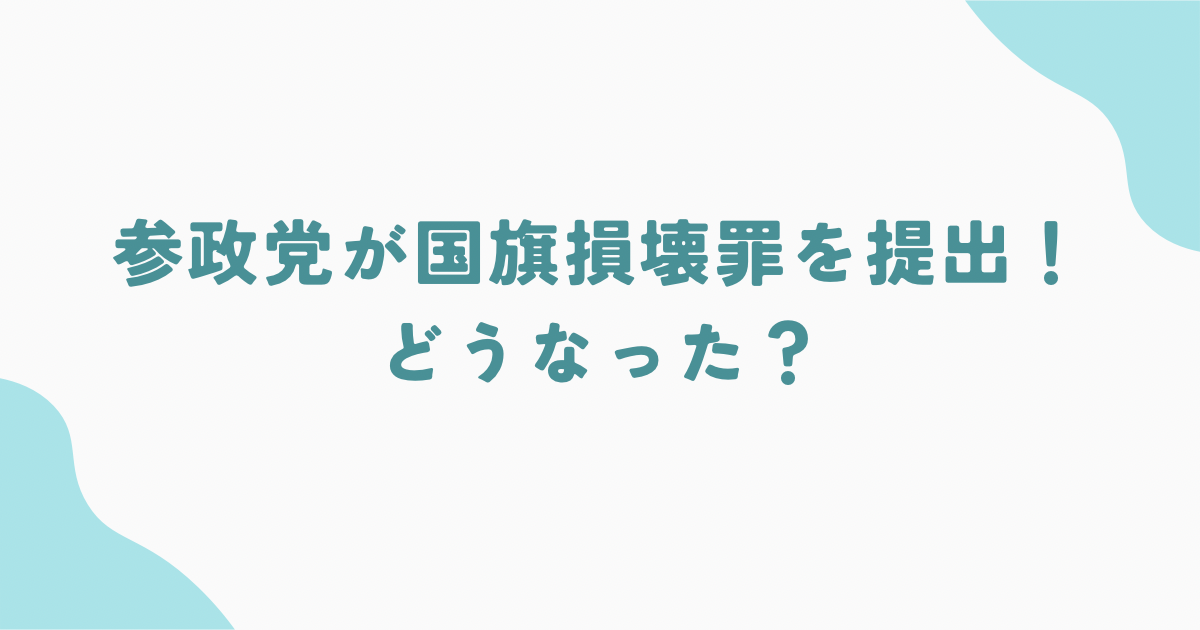2025年10月、参政党が「国旗損壊罪」を新設する刑法改正案を参議院に単独提出しました。
日本国旗を損壊した場合に刑罰を科すというこの法案は、「国旗を守るべきだ」という意見と、「表現の自由を制限する恐れがある」という懸念の両方から注目を集めています。
今回は、この法案の内容や他党の反応、そして賛成・反対それぞれの主張をわかりやすく解説します。
参政党が提出した「国旗損壊罪」とは?
参政党が提出した改正案は、「日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗や国章を損壊・汚損した者」に対し、
**「2年以下の懲役または20万円以下の罰金」**を科すというものです。
現行の刑法では「外国の国旗や国章を損壊した場合」は犯罪になりますが、日本の国旗(日の丸)に関しては処罰規定が存在しません。
参政党はこの「矛盾を解消するため」として法案を提出しました。
神谷宗幣代表は、「他国の国旗を尊重するのと同じように、自国の国旗も大切にすべき」と強調しています。
今回の法案は、参政党として初めての単独提出法案となりました。
他党の反応 ― 維新・自民も前向き姿勢
日本維新の会の吉村洋文代表は、「外国国旗は守られているのに自国の国旗が守られていないのはおかしい」と述べ、方向性としては賛同する姿勢を見せています。
ただし、「事前に一声かけてほしかった」とも語り、今後は自民・維新・参政の3党で協調しながら法案成立を目指す構えです。
自民党も来年の通常国会で「日本国国章損壊罪」の制定を掲げており、連立合意の中でも明記されています。
そのため、今後の国会審議では、これら3党による共同提出または修正版の提出なども視野に入っています。
他国ではどうなっている?国際的な比較
国旗を守るか、表現の自由を守るか──。
この問題は日本だけでなく、世界中で議論が分かれています。
各国の法制度の違い
各国における国旗損壊の扱いは次のようになっています。
アメリカでは、国旗を燃やしたり破ったりする行為は「表現の自由」として憲法で保護されています。そのため、国旗損壊に対する罰則はありません。
ドイツでは、国旗を損壊する行為は「国家侮辱罪」の一部として処罰の対象となります。国家の象徴を傷つける行為として厳しく規制されています。
韓国には「国旗冒涜罪」があり、国旗を汚したり破ったりする行為は犯罪として罰せられます。国家への敬意を重んじる姿勢が法律にも反映されています。
フランスでも、公共の場で国旗を侮辱する行為は処罰の対象となり、罰金刑が科されることがあります。ただし、非公開の場所での行為については必ずしも処罰されるとは限りません。
一方、日本には国旗損壊を直接罰する明確な法律は存在しません。外国の国旗を損壊した場合には刑法で処罰されますが、日本国旗に関してはそのような規定がないのが現状です。
賛成派の主張
参政党や保守派を中心とする賛成派は、「国旗は国家の尊厳そのもの」と考えます。
国旗を損壊する行為は、国家や国民に対する侮辱であり、社会的秩序や愛国心を損なう行為とみなされます。
賛成派の主なポイント
国旗を守るのは国民として当然の責務 他国では処罰されており、日本も同様の基準を設けるべき 国旗を侮辱する行為は、表現ではなく「冒涜」
SNSで「炎上目的」に国旗を損壊する動画などが拡散される現状を問題視する声も強く、
「自由の名のもとに国家への侮辱を許してはいけない」という意見が主流です。
反対派の主張
立憲民主党や共産党、憲法学者などリベラル派を中心とする反対派は、
最大の懸念として**「表現の自由」への侵害**を挙げています。
反対派の主なポイント
憲法21条で保障された表現の自由が制限される可能性 「侮辱」の定義があいまいで、恣意的な運用の危険がある 政府批判やアート表現まで処罰対象になるおそれ
特に、「どこまでが侮辱か」を判断するのは主観的であり、
政権に批判的な表現が“国を侮辱した”として処罰される可能性も否定できません。
反対派は、国家権力が表現内容をコントロールすることへの警戒感を強く示しています。
論点は「自由と敬意のバランス」
国旗損壊罪をめぐる最大のテーマは、
**「国家の象徴を法で守るべきか」それとも「個人の自由を優先すべきか」**という価値観のバランスです。
国旗を尊重することは大切ですが、
一方で言論や表現の自由が狭まれば、民主主義の根幹が揺らぐ可能性もあります。
特にSNS時代では、誰もが情報発信者となるため、
曖昧な法律が誤解や過剰反応を招くリスクも指摘されています。
この法案は、「愛国心」と「自由社会の維持」をどう両立するか──
日本社会が改めて向き合うべきテーマを突きつけているといえるでしょう。
まとめ
参政党が提出した「国旗損壊罪」をめぐる議論は、
単なる法律問題ではなく、日本人の価値観や民主主義のあり方を問うものです。
国旗を守ることで国家の尊厳を保つべきという立場 表現の自由を守り、権力による規制を警戒する立場
どちらの主張にも一理があります。
今後の国会審議では、感情論に流されず、国民全体で「自由と敬意のバランス」を見極める冷静な議論が求められるでしょう。