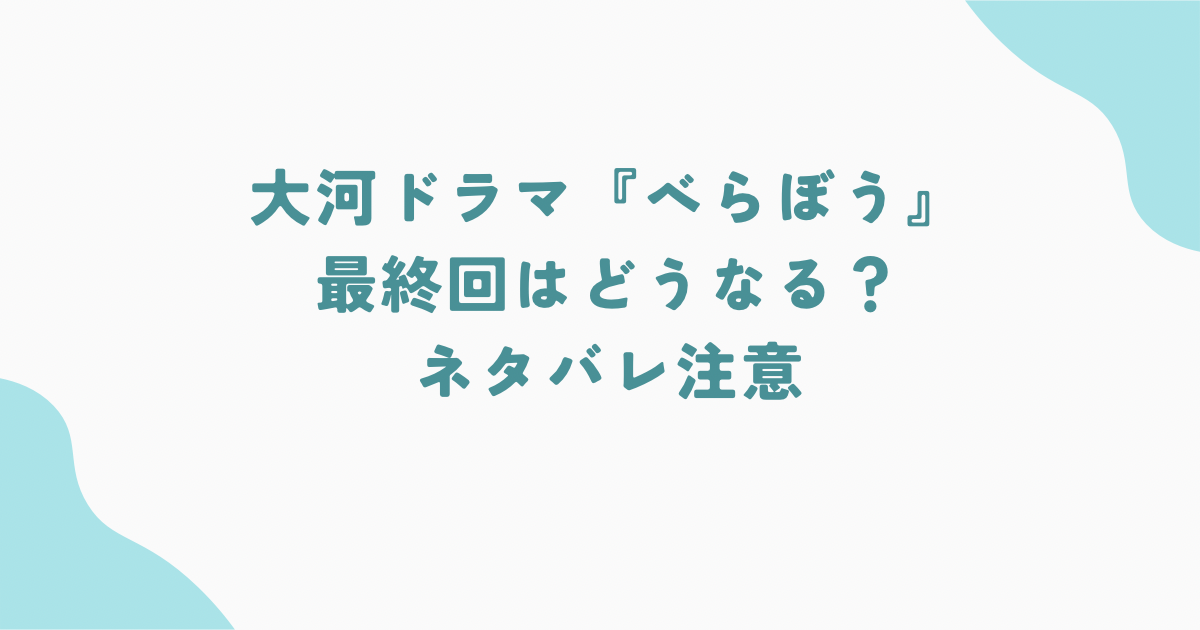2025年大河ドラマ『べらぼう』もついにクライマックスへ。
写楽誕生から出版界の革命を起こした主人公・蔦屋重三郎(蔦重)の物語は、どのような最期を迎えるのでしょうか?
この記事では、最終回第48話の展開をわかりやすくまとめつつ、史実とドラマならではの演出の違いにも触れていきます。
ネタバレを含みますのでご注意ください。
大河ドラマ『べらぼう』最終回のあらすじ
◆消えゆく“写楽”――プロジェクトの終幕
再建した耕書堂で写楽絵の出版を続けていた蔦重でしたが、写楽ブームも終わりを迎え、ついに“東洲斎写楽”プロジェクトが静かに幕を下ろします。
歌麿を中心に多くの絵師や戯作者が集まった“夢のチーム”は解散し、宴では互いへの労いと友情が語られます。
特に歌麿がていへ告げる感謝の言葉は、写楽という存在がいかに多くの想いを乗せて作られたかを象徴する名シーンとなっています。
◆本居宣長との出会いが導く、新たな「志」
ある日、ていが預かった忘れ物の本『玉くしげ』がきっかけで、蔦重は国学者・本居宣長の思想に興味を抱きます。
儒学一辺倒だった幕府の価値観に疑問を投げかける宣長の哲学に深く共鳴した蔦重は、松平定信へ書物を届けた後、宣長本人に会うため伊勢松阪を訪問。
「本屋には、人々に知るべきことを届ける使命がある」——その信念から、宣長の学問を江戸に広めることを申し出ます。
宣長も蔦重の情熱を認め、二人は手を取り合うことになります。
◆吉原再建へ動き出す蔦重
一方、吉原の窮状を知った蔦重は、経営不振の実態を自ら調査。
女郎の待遇悪化、芸者の値下げ競争、廃業する料理屋……かつて華やかだった町は混乱の最中にありました。
蔦重は「新吉原町定書」をまとめ、吉原全体の立て直しを図ることを決意します。
困っている人を放っておけないその姿に、ていは古代中国の商人・陶朱公の教えを思い出し、夫の覚悟を静かに見つめるのです。
蔦重を襲う“脚気”と最期の時間
◆次世代を育てながら、病が忍び寄る
十返舎一九、曲亭馬琴ら若い才能を育て、出版界を盛り上げることに力を注ぐ蔦重。
しかし、1796年の秋、ついに脚気で倒れてしまいます。
衰弱しながらも筆を持ち続ける姿に、周囲の仲間たちは胸を締め付けられます。
◆“昼九つに迎えが来る”という予告
ある夜、蔦重は不思議な夢を見たと語り、「明日の昼九つ(正午)にお迎えが来る」と告げます。
ていは蔦重亡き後の耕書堂の後継、戒名、墓石に至るまで全てを準備しながら、夫の最期に寄り添う覚悟を固めていました。
◆迎える最期――そして奇跡の一瞬
正午の鐘が鳴り響き、蔦重は息を引き取ったかのように見えます。
仲間たちは涙を流しながらも、「呼び戻すぞ」と大田南畝が叫び、必死に踊り始めます。
その空気を切り裂くように——蔦重が再び目を開き、微笑むのです。
拍子木の音とともに、“蔦重の人生の語り部”のような九郎助稲荷が幕引きを告げ、物語は静かに終わりを迎えます。
史実の蔦屋重三郎はどうだったのか?
◆本当の最期はどう迎えた?
史実では蔦屋重三郎は1797年、48歳で死去。
自身で「正午に死ぬ」と予告したものの、その時間には亡くならず、夕刻に息を引き取ったと伝えられています。
ドラマの演出は、この逸話を膨らませて感動的な形に再構成したものと考えられます。
◆耕書堂の跡を継いだのは誰?
実際の耕書堂は、番頭の「勇助」が二代目として店を継ぎ、「二代目蔦屋重三郎」を名乗りました。
ドラマでも歌麿と関連づけるような描写がありますが、史実の勇助とは別の人物です。
二代目は北斎をはじめ多くの人気作家を起用し、約36年にわたり店を守りました。
まとめ
大河ドラマ『べらぼう』最終回は、蔦屋重三郎が信念を貫き、仲間たちに見守られて最期を迎える感動的な物語です。
写楽プロジェクトの終焉、本居宣長との出会い、吉原再建への奔走、そして脚気との闘い——。
出版に人生を捧げ、「江戸の文化を未来へ繋ぐ」という志を最後まで持ち続けた蔦重の生き様が鮮やかに描かれています。
史実の逸話も巧みに取り入れつつ、ドラマならではの温かさとユーモアで締めくくられた最終回でした。