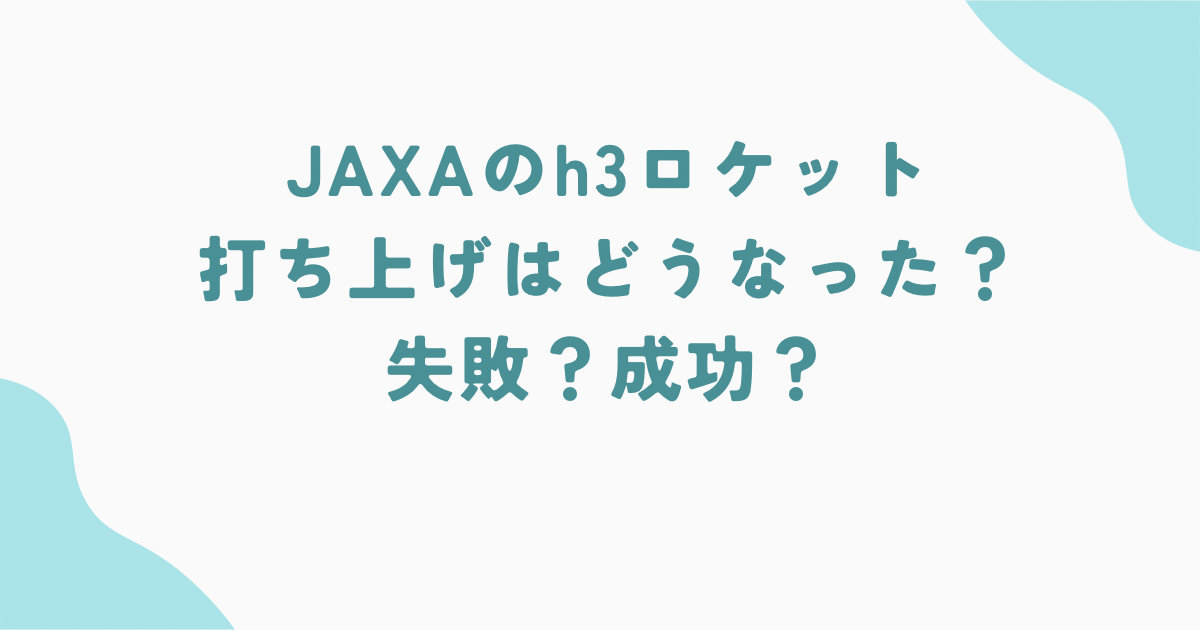日本の次世代主力ロケット「H3ロケット」が、ついに新たなステージへと進みました。
2025年10月21日に実施された「H3ロケット7号機」の打ち上げでは、注目の“24形態”が初飛行。
過去の失敗を乗り越えた日本の宇宙技術の進化と、次世代補給船「HTV-X」の活躍に注目が集まっています。
H3ロケット7号機の打ち上げはどうなった?
JAXA(宇宙航空研究開発機構)と三菱重工が共同開発した「H3ロケット」。
H-IIAの後継機として2024年から本格運用が始まったこのロケットは、今回の7号機で節目を迎えました。
10月21日に種子島宇宙センターから打ち上げられた「H3ロケット7号機」は、新型宇宙ステーション補給機「HTV-X 1号機」を搭載。
そして今回の打ち上げは、“24形態(H3-24W)”の初飛行という点でも大きな意味を持ちます。
この「24形態」は、1段目にLE-9エンジンを2基、補助ロケット(SRB-3)を4本装備。
最大で静止トランスファー軌道(GTO)に6.5トン級の衛星を打ち上げられる、高出力仕様です。
結果は――
打ち上げ成功!
H3シリーズとして5号機から続く成功記録を更新し、完全に安定した運用段階に入りました。
H3ロケットとは?
H3は、約20年間日本の宇宙開発を支えてきたH-IIAの後継機。
開発の目的は「コスト半減」と「信頼性・柔軟性の向上」です。
打ち上げ費用は従来のH-IIAの半分となる約50億円台を目標としており、
人工衛星ビジネスや国際的な打ち上げ競争でも優位に立てるよう設計されています。
また、構成を柔軟に変えられる点も特徴。
H3は、エンジン数や補助ロケットの有無によって複数の「形態」が存在し、
打ち上げる衛星や目的に応じて構成を変えられます。
「24形態」は最強仕様!
今回の7号機で採用された「24形態」は、現時点で最も強力な仕様です。
LE-9エンジン2基+SRB-3を4本搭載し、大型通信衛星などを静止軌道まで運ぶ能力を持ちます。
H-IIAよりも安定した燃焼性能と低コストを実現し、
“日本版ファルコン9”とも呼ばれるほどの進化を遂げています。
一方で「30形態」には課題も?
順調な「24形態」とは対照的に、開発中の「30形態」では課題が判明しました。
この構成は、SRBを使わずに1段メインエンジンを3基搭載するという日本初の設計で、
中型衛星の低コスト打ち上げを目的としています。
しかし、2025年7月に行われた燃焼試験で、タンク圧力が想定より低下する現象が発生。
調査の結果、3基目のエンジン系統で推進剤タンクの加圧が不十分だったことが分かりました。
この問題は24形態などには影響しませんが、30形態の初飛行は2026年度以降に延期される見通しです。
HTV-Xとは?「こうのとり」後継の新型補給船
今回H3ロケットに搭載された「HTV-X(エイチティーヴィー・エックス)」は、
国際宇宙ステーション(ISS)への物資補給を担う新世代の補給機です。
従来の「こうのとり(HTV)」よりも軽量化・高性能化され、
電力供給や冷却機能を強化。24時間前までの積み込みにも対応し、
より柔軟な運用が可能となりました。
また、補給任務を終えた後も「宇宙実験プラットフォーム」として再利用でき、
最長1年半、軌道上での技術実証を行うことができます。
HTV-X 1号機は、打ち上げから約5日後にISSへ到着予定。
ロボットアームで把持され、ISSへ接続される計画です。
日本の宇宙開発、次の10年へ
2023年のH3試験機1号機では、残念ながら打ち上げに失敗しました。
しかし、JAXAと三菱重工は原因を徹底的に分析し、改良を重ねた結果、
2号機以降はすべて成功。
今回の7号機の成功により、H3ロケットは完全に信頼できる主力ロケットとしての地位を確立しました。
H-IIAの引退(2025年6月)を経て、
日本の宇宙輸送の未来は、いよいよH3の時代へと移り変わっています。
まとめ
2025年10月21日に打ち上げられた「H3ロケット7号機」は、
“24形態”の初飛行に成功し、HTV-X 1号機を無事軌道に投入しました。
失敗から立ち直ったH3ロケットは、今や日本の宇宙輸送の中心的存在です。
今後は、課題を抱える「30形態」の改良や、探査ミッションへの拡大も期待されています。
これからの10年、日本の宇宙開発の躍進に注目していきましょう。