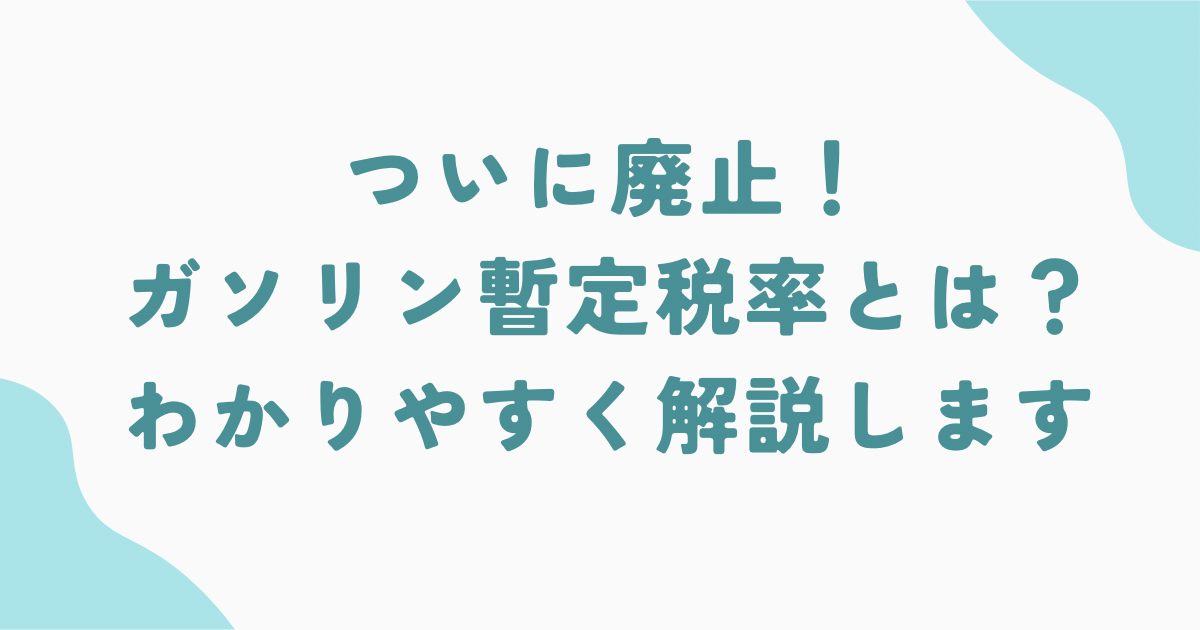ついに、ガソリンの「暫定税率」が50年の歴史に幕を下ろします。
1974年に導入されて以来、「一時的な税」と言われながらも半世紀にわたり続いてきたガソリンの上乗せ税が、2025年12月31日で廃止されることが決まりました。
この記事では、そもそもガソリン暫定税率とは何か、なぜ続いてきたのか、そして廃止によって私たちの生活にどんな影響があるのかを、わかりやすく解説します。
ガソリン暫定税率とは?
ガソリン暫定税率とは、本来のガソリン税に一時的に上乗せされている税金のことです。
1974年に道路整備のための財源を確保する目的で導入されましたが、その後も延長が繰り返され、実質的には「恒久的な税」となっていました。
現在の税率の内訳
本則税率:28.7円/リットル 暫定税率:25.1円/リットル 合計:53.8円/リットル
つまり、1リットルあたり約半分が「暫定税率」という名の上乗せ分だったのです。
導入の背景と「暫定」のまま続いた理由とは?
導入のきっかけはオイルショック
1970年代のオイルショックにより、道路整備のための国の財源が不足したことがきっかけでした。
当初は「2年間の時限措置」として導入されましたが、景気や財政の状況から延長が繰り返されることになります。
「暫定」が外れなかったワケとは?
その後も道路整備やインフラ維持のための重要な財源として使われ続け、結果的に約50年もの間「暫定」という名のまま残りました。
2009年には「道路特定財源制度」が廃止され、2010年からは「当分の間税率」という名称に変更されています。
問題視されていた理由は?
ガソリン暫定税率は長年にわたり、次のような問題点が指摘されてきました。
「暫定」の名のまま50年続いている ガソリン価格の高騰に拍車をかけている 税金にさらに消費税がかかる「二重課税」状態
特に近年は、ガソリン価格の高止まりが続いていることもあり、「暫定税率を廃止してほしい」という声が強まっていました。
ガソリン暫定税率廃止が決定!いつから?どのくらい安くなる?
2025年10月31日、自民党・日本維新の会・公明党・立憲民主党・国民民主党・共産党の6党が旧暫定税率の廃止で合意しました。
ガソリンの場合
対象:旧暫定税率(25.1円/リットル) 廃止日:2025年12月31日 想定値下げ幅:約15円/リットル(消費税除く) → 例)175円/L → 約160円/Lへ
軽油の場合
対象:旧暫定税率(17.1円/リットル) 廃止日:2026年4月1日
補助金との「つなぎ措置」
廃止までの間は、補助金で段階的に価格を引き下げる予定です。
11月13日:10円 → 15円 11月27日:20円 12月11日:25.1円(旧暫定税率分) その後、12月31日に補助金を終了し、正式に税率廃止に切り替えられます。
廃止で減る税収は?財源はどうなる?
旧暫定税率を廃止すると、年間で以下の税収が減る見込みです。
ガソリン:約1兆円 軽油:約5,000億円
そのため、政府・与野党6党は以下の方針を示しています。
歳出改革の推進 法人税の特別措置の見直し 超富裕層への課税強化 一時的には「税外収入」で対応
また、道路やインフラ保全のための安定財源を1年後をめどに確保することでも一致しています。
廃止で私たちの生活はどう変わる?
家計の負担軽減
ガソリン代が15円ほど下がれば、車通勤や配送業など燃料を多く使う人には大きな節約効果が期待されます。
物流コストの抑制
燃料費が下がることで、運送業や物価全体にもプラスの影響が及ぶ可能性があります。
ただし、税収減の影響から、今後別の形で財源確保が求められる可能性もあり、注意が必要です。
まとめ
ガソリンの「暫定税率」は、1974年に一時的な措置として導入された税金でした。
しかし実際には、約50年間続く「事実上の恒久税」となっていました。
2025年12月31日をもって、この暫定税率がついに廃止されます。
ガソリン価格は15円前後下がる見込みで、家計への負担軽減が期待されています。
一方で、年間1兆円を超える税収減への対応や新たな財源確保など、今後の議論も注目されます。
半世紀続いた“暫定”が終わる今、日本の税制とエネルギー政策は新たな転換点を迎えています。